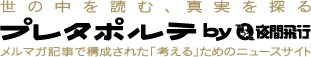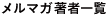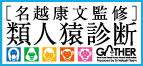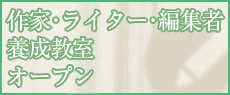ハザードテープの向こう側
『赫獣』では、怪物が起こした惨劇の跡が繰り返し描写される。森林では、樹木に人体の欠片が引っかかっており、辺りには濃い血の匂いが残っている。
あるいは、人間側の激戦を示す、散弾で穴だらけになった樹皮。モズの生贄のように枝に腹を突きさされたままの遺体。
かつてゴジラに対抗して大映が生み出した人気怪獣ガメラの、平成の時代になってからの復活第一作である『ガメラ 大怪獣空中決戦』(95)もまた、「怪獣が初めて出る世界」の物語だったが、当時装飾のスタッフであり、後に脚本家となった長谷川圭一は、ガメラの天敵ギャオスによって破壊された家屋の飾り付けをしている時、事故でも災害でもない「人知を越えたもの」の破壊を表現できることに、打ち震えるような感動を覚えたという。
『ガメラ 大怪獣空中決戦』には、女性科学者が、ギャオスによって犠牲になった恩師の死を、ギャオスの吐瀉物に手を突っ込んで取りだしたメガネの存在によって知るという場面がある。
美人科学者が、作業用の手袋は付けているものの、溶けた恩師の身体に直に手を突っ込むということにはゾクゾクさせられるし、それは同時に、怪獣という未知のものに触れるという<臨界点に手をつける>経験にもなっている。怪獣映画として忘れられない秀逸な描写だった。
『赫獣』でも、けもの道で大型糞が見つかり、怪物の経路の一部が分かるという描写があるが、それだけでも心ときめくものがある。むろん私がスカトロマニアだからではない。怪獣という架空のものの「痕跡」が日常空間に残留していることの興奮がそこにあるのだ。
『赫獣』では黄色いハザードテープの向こう側に犠牲者の遺品を見て、主人公格の人間が心を痛める場面がある。
既に境界面の向こうから何かが出現し、だがその地点はさえぎられて一般人が自由に出入りすることも出来ない。
「この扉の向こうには、何があるのか」
そんな心のざわめきが、怪物というものの存在をより大きくさせる。
現実に怪獣が出現したら
『仮面ライダークウガ』(00~01)というテレビ番組は、等身大ヒーローアクションだが、作りとしては怪獣映画の方法論が用いられている。怪人による被害はまったく人間からは理解も及ばない無差別なものとして現れ、現実世界と同じく警察がそれに対処する。
脚本を書いた荒川稔久は、実際に埼玉県警に電話して「もし怪物が出たらどう対処しますか?」と取材した。その時警察は、熊の被害に喩えて説明したという。
『赫獣』において、当初怪物による被害は「食害」とみなされ、害獣を「殺処分」するという認識を人間側は持っていた。
ペットや家畜の食害報告があり、犬やウサギ、猫がバラバラになる事件が予兆として起きていたのだ。同様の描写は、『フランケンシュタイン対地底怪獣』にもあり、怪獣ファンとしては嬉しくなる。
『赫獣』で怪物の正体は熊か野犬、ヒグマではないかと推測が立てられるが、たとえば口径が合わないなどということがわかることで、既知の情報では処理できないことに作中世界の人間たちが気づかされていく。
つまり怪物の存在は、現実にあるものを足がかりにし、それが「ない」ということが証し出されることで、逆に明らかになるのだ。
警察は食害獣を「ヰ号」と仮称していたが、やがてそれが一匹ではなかったことがわかる。
前述した『フランケンシュタイン対地底怪獣』の続編『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』(66)は、前作のフランケンシュタインの細胞が二つに分裂して争う物語だが、怪物が二体いることがわかった時、自衛隊は「以後、海のフランケンシュタインをガイラ、山のフランケンシュタインをサンダと呼称する」と発令。
海だからガイラ、山だからサンダという記号的な名称が、現実と架空の境界を示すようで怪獣ファンにはたまらない「名づけ」の場面である。
それは『赫獣』で怪物が「ヰ号」「ウ号」と記号的に呼ばれていることの原点であるように、僕には感じられた。
『仮面ライダークウガ』において、怪人は「未確認生命体」と呼ばれ、それと戦うクウガもまた、当初怪人と同じ存在とみなされ「未確認生命体4号」(劇中で四番目に人目に触れたため)と呼ばれていたのも、これと通じる精神だろう。
怪物と相対する存在
徴兵もないのが当たり前な戦後社会に育った日本人は、たとえ銃を持った警察官でも、実際の事件で発砲した経験など少ないのが普通だ。
そこで『赫獣』でははじめ、機動隊上がりでピストルの腕前を競った者どうしや、「バスジャック班を射殺して出世」した者など、「ピストル専門警官」と呼ばれる警察官が怪物と相対する存在に選ばれる。
そしてこの小説において、「バケモノ相手の『狩り』」と呼ばれる行為の一番の担い手は、怪物が出現した山で、狩りをやりながら人里離れた小屋に住む戦争経験者の韓老人が務めている。
彼にとって、怪物との対決は、戦争体験の反復でもあった。この設定にするためか、『赫獣』で描かれる現在の時制は「1984年」となっている。ちなみに「1984年」とは、後の平成ゴジラシリーズの起点として、人類の宿敵としてのゴジラがスクリーンに復活した年でもある(『ゴジラ』橋本幸治監督)。
人嫌いで、眼光だけで周囲を怯えさせるだけの雰囲気をまとっている韓老人だが、無慈悲な殺戮を繰り返す怪物に向き合いながら、かつての戦争では「自分がどれだけ存在できたはずの人間を殺してきたか」と考える。
平和な時代には、戦争で人を殺したことがあるというのは、それ自体「汚れ仕事」とみなされる。
『赫獣』の作者・岸川真は、韓老人が惨劇に向き合うたびに「殺した兵士たちの血を思い出させた」などと、戦争体験の心理的反復を執拗に書いていく。
日常的な範疇を越える暴力をふるう怪物との戦いは、平和な日本で囲い込まれた感覚を解除しなければ向き合えないということを繰り返し示すためだろう。
重傷を負ってこん睡状態にあっても「俺は、銃が欲しい」という意志だけで復活するこの韓老人が在日韓国人であり「警官が苦手でな」と言うのも、この戦いがアウトカーストに属するものであることを読者に認識させるためと思われる。
他にも、親が原爆症の子、知恵おくれの子など、社会の平均像から外れた人々を、岸川はやや過剰なくらい作品世界に投入してみせる。
『フランケンシュタイン対地底怪獣』では、放射能で身体も力も増大化するフランケンシュタインの怪人と対比するように、同じ放射能で白血病になり死を待つばかりの少女が登場していた。この映画が作られた時点で、既に原爆の被害の記憶は一般の人々にとって過去のものとなっていた。
怪獣映画はもともと、眠っていた過去の爪痕がまだ生きていることを示すものなのだ。
韓老人は、17歳からずっと戦争にかかわってきたという。
彼が育った慶州で猟をしていた時、日本軍の流れ弾で父を喪う。日本人に復讐しない彼を地元の人間はなじるが、父を手厚く葬ってくれた日本軍に逆に入って、兵士となった。
感情に任せた怒りは何も生まず、戦闘においても命取りになると知っていた韓老人だが、怪物により知恵遅れの無心な少女が無残に強姦され殺された時、初めて純粋な怒りが湧いてくる。そして「実は俺は日本兵に復讐したかったのかもしれん」と自覚する。
そう。怪物の存在は戦争体験すら凌駕する。怪物は制御なき怒りを呼び覚ますのだ。


その他の記事

|
「AI色」の未来は避けられない(高城剛) |

|
電気の「自炊」が当たり前の時代へむけて(高城剛) |

|
「対面力」こそAIにできない最後の人の役割(高城剛) |

|
2017年、バブルの時代に(やまもといちろう) |

|
ヘッドフォンの特性によるメリットとデメリット(高城剛) |

|
私事ながら、第4子になる長女に恵まれました(やまもといちろう) |

|
「映画の友よ」第一回イベントとVol.033目次のご案内(切通理作) |

|
アーユルヴェーダを築いた修行者たちを偲ぶ(高城剛) |

|
辻元清美女史とリベラルの復権その他で対談をしたんですが、話が噛み合いませんでした(やまもといちろう) |

|
上野千鶴子問題と、いまを生きる我らの時代に(やまもといちろう) |

|
脳の開発は十分な栄養がなければ進まない(高城剛) |

|
貧乏人とおひとり様に厳しい世界へのシフト(やまもといちろう) |

|
国民投票サイト「ゼゼヒヒ」は何を変えるのか――津田大介、エンジニア・マサヒコが語るゼゼヒヒの意図(津田大介) |

|
急成長する米国大麻ビジネスをロスアンゼルスで実感する(高城剛) |

|
週刊金融日記 第269号 <性犯罪冤罪リスクを定量的に考える、日経平均株価2万円割 他>(藤沢数希) |